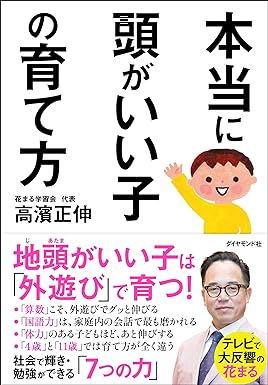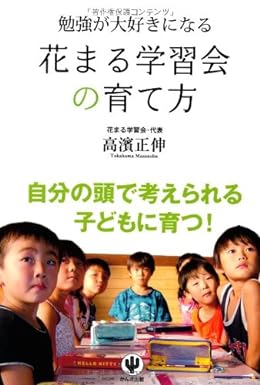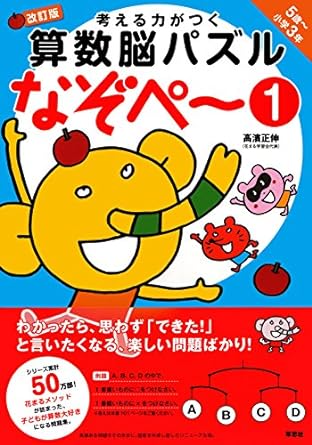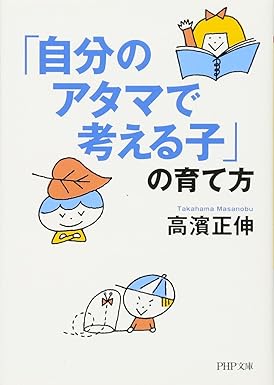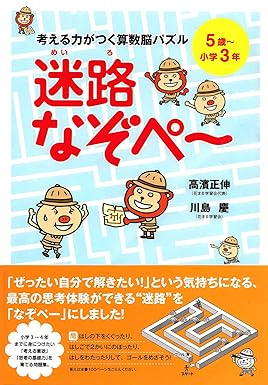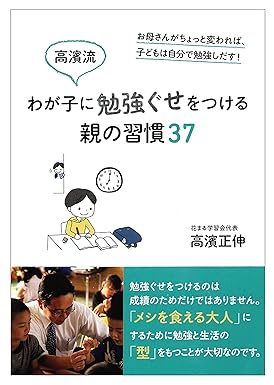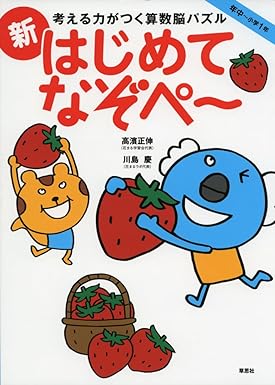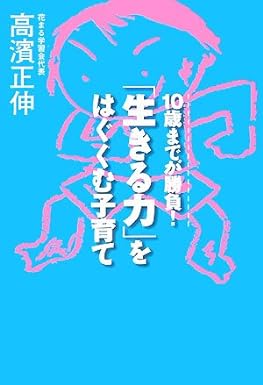【算数脳】って?
「算数脳」とは、将来、数学の問題を解くカギとなる思考脳力のことを、「小3までに育てたい算数脳 」の著者:高濱正伸氏が使い始めた言葉です。
」の著者:高濱正伸氏が使い始めた言葉です。
例えば、算数脳が育っていると、図形問題や空間把握の問題を解くのに必要な補助線が自然と見えてくるチカラのこと。
この脳力も「算数脳」の一つです。
この算数脳を持たない教え子に補助線の引き方を教えても、別な図形問題を自ら補助線を導き出すことは、至難の技なのです。
だから、算数脳を持たない人たちには、数学の難問(図形・空間把握力)が、最も苦手意識の強い分野になってしまうのです。この著書では、本能的に補助線が見えることがいかに重要であることかについて語っていらっしゃいます。
一方、数学を得意とする人は、難問であればあるほど、その問題へチャレンジする意欲が湧くといいます。我が子を、そんな意欲旺盛なチャレンジャーに育てるには、親の意識改革が必要であると、高濱正伸氏は言います。
【算数脳を育てるヒント!】
それなら、立体的な空間把握力を身に付けさせて、将来、数学を得意にさせてあげたいというのは、親なら誰もが願うことでしょう。
でも、それは、いったいどうやって身に付くものなのでしょうか?
そのためにも、知っておかないと後悔する説があることを、まずお話ししておきましょう。
それは、算数オリンピックの出題問題を作る数学オリンピック委員の経歴を持つ高濱正伸著「小3までに育てたい算数脳 」に、以下のようなことが書かれています。
」に、以下のようなことが書かれています。
その① 一番大事なことは、机上でプリント学習することによって、「算数脳」を育てようとしないことである。(つまり、実体物による遊びが重要であるということです。)
その② 空間把握力には、『臨界期』があり、その時期は「小学校3年生くらいまで」ということです。それ以降の学習では、頭の中に空間をイメージする脳力を育てることができないので、出題問題のパターン練習を繰り返すことでしか、問題を解くことができなくなるということなのです。
⇒恐ろしいことに、図形や空間把握の問題を勉強し始めるのは、その小3以降なのですから、空間把握力が育っていないと、最初から、パターン練習の道しかなくなってしまうということになります。
【なぜ、高濱氏は、幼少期の外遊びを重要だと考えるのか?】
高濱正伸著「小3までに育てたい算数脳 」では、幼少期の外遊びがとても重要だと書いていますが、外遊びのメリットには、どのようなことがあるのでしょう?
」では、幼少期の外遊びがとても重要だと書いていますが、外遊びのメリットには、どのようなことがあるのでしょう?
①外で身体をしっかり動かすことは、たくさんの酸素を吸い込み、脳の働きを活発にしてくれます。これは、モンテッソーリ教育においても、同じことが言われています。
また、高さのある遊具などに恐怖心に負けずに上っていこうとするチャレンジ精神や、鉄棒の逆上がりができるようになるまで頑張る!といった根性(精神力)などを鍛えることもできます。
②子ども達だけでのグループ遊びをする時に、子ども達だけで(親が関わらずに)仲良く遊び、より楽しく遊べるようにと、ルール作りなどを考えて遊ぶことで、柔軟な思考力に繋がっていきます。(親の指示だけで遊んでいない時)
例:幼少期なら、親は、「○○ちゃんは、まだ小さいからこんな遊び方では、可哀想じゃない?」などと、子ども達がどうすればいいのか?どんなルールを作ると、みんなが楽しく遊べるのかなどを問題提起し、子ども達だけで問題解決をするよう考えさせてあげるきっかけ作りをするといいですね。
③砂遊びも創造力を掻き立てますし、ジャングルジムでいろいろな角度から異なる風景を見たり、シーソーで「重さ」を体験したり、ボール投げで距離(長さ)などを競ったり、縄跳びで飛べた数を競ったり、遊具などでも算数に関係したものがたくさん存在します。
④「脳を育て、夢をかなえる―脳の中の脳「前頭前野」のおどろくべき働きと、きたえ方  の著者」川島 隆太
の著者」川島 隆太 教授も、親子の会話や友達との遊びが前頭前野を働かせる‥とおっしゃっておられます。
教授も、親子の会話や友達との遊びが前頭前野を働かせる‥とおっしゃっておられます。
このような様々な外遊びの体験から、やり直す根性や精神力を鍛え、身体(脳の活性)を鍛え、実体験を積むことができるのです。
このような考え方から、学校準拠ではなく、考える力を養うことにポイントをおいている通信教材が、「名探偵コナンゼミ 」になります。
」になります。
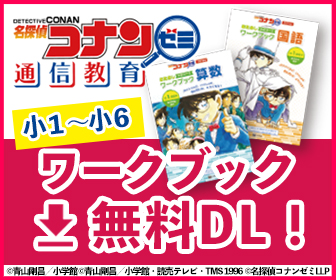
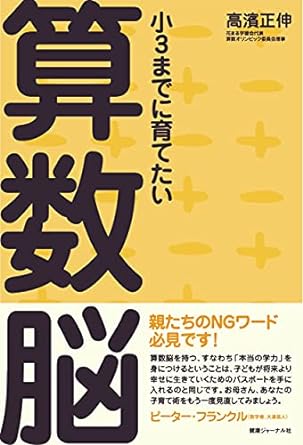
」の著者:高濱正伸氏が使い始めた言葉です。