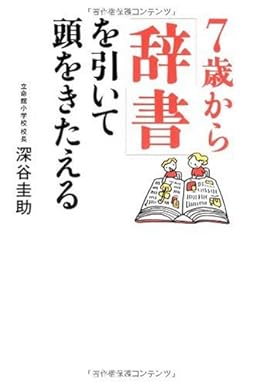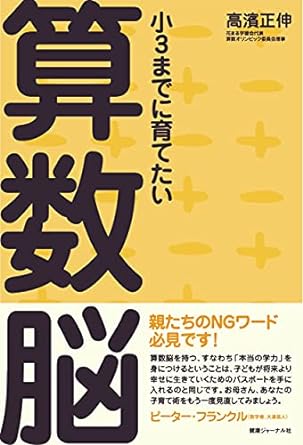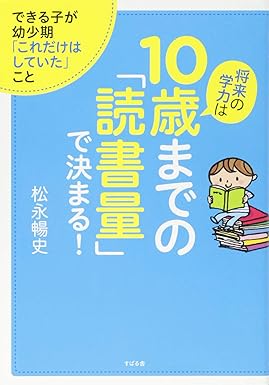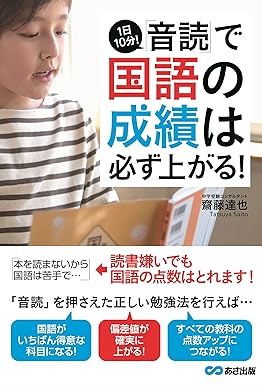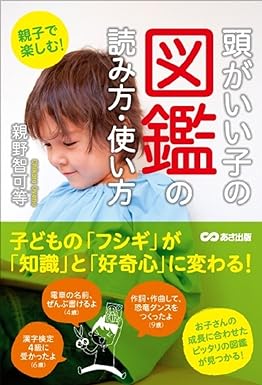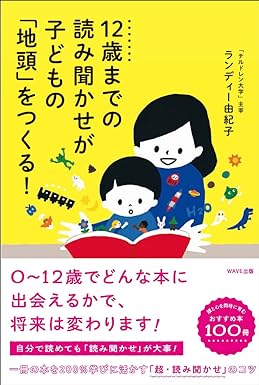-PR-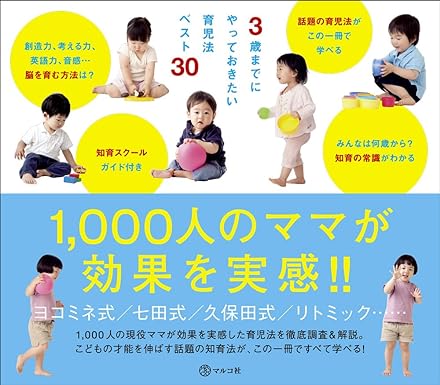 3歳までにやっておきたい育児法ベスト30 |
幼少期に早期教育に取り組み、誰よりも優秀に育っていたはずなのに、ある時点から急に成績が伸び悩むということがあります。
それには、いくつかの早期教育に間違った認識があることが指摘されています。
≪その①ー『先行学習』と『地頭を良くする知育』の違い≫
『先行学習』とは、平仮名をはじめとした文字を覚えたり、足し算・引き算などの四則計算を幼少期から始めることです。
これらは、知能の発育を促すための学習ではなく、その道具に過ぎません。思考力を使わなくても、小学校低学年くらい(学校の授業授業により)で、誰でも習得できるものです。
つまり、これらを誰よりも早く、幼少期から覚えたからと言って、知能が発達した優秀児になるわけではないのです。
このような学習方法を「先行学習」と言います。
誰よりも、先行して学んでいるだけなので、学校の授業についていくには十分な学力がついています。
そのため、授業中に先生の話しを聞かなくても満点をとることもできるので、自分の実力を過信しやすくなります。
その結果、先生の説明を聞かない習慣がつく可能性もあります。
そのうち、先行学習が授業に追いつかれ、成績が落ち始めるということがあります。
さらに、みんなに優秀と思われているため、分からないところを質問することが恥ずかしくて躊躇するようになると、ますます成績が落ちてしまいます。
このように、「自分は優秀なのだ!」と思いこむと「一生懸命勉強しよう!」という気持ちを薄れさせてしまうこともあるのです。
幼児教材会社ヴィッテ式家庭保育園が参考にしていたヴィッテの父親は、その自信過剰になることをとても警戒したそうです。
だから、父親はヴィッテの周囲にいる人たちに「どんなに難しい問題を正解できても、褒めないで下さい」とお願いをし、ヴィッテには「お前は、みんなより先に知っているだけに過ぎないのだ!」と言い聞かせながら育てたと言います。
≪その②ー『先行学習』は何のため?≫
文字を早く覚えることによって、たくさんの本を自分で読むことができるようになります。そして、社会を広く知っていくことに活用しなければ、そもそも文字を覚えた意味が無いのです。
書物は「知恵の宝庫」とも言われています。
幼少時から、文字や難しい漢字、豊富な言葉を覚えたら、それだけ、高度な知識を身につけることができます。
しかし、文字を覚えれば、どんな専門書を読んでも理解できるわけではありません。
だから、文字を覚えても、百科辞典や漢字の多い本を一人で読むことが難しい年齢の間は、『7歳から「辞書」を引いて頭をきたえる 』(深谷 圭助著
)のようなことを行なうと良いと、私立の幼稚園・小学校でとり入れ始めるようになりました。
文字を読めるようになったら、次に「言葉の意味を知ろう!」ということです。そうしてはじめて、読解力の向上につながっていきます。
一方、四則計算についても、幼稚園時代にできるようになったからと言って、知能が優秀な証拠と言える訳ではありません。それは、ただ、数の操作方法を知ったに過ぎないからです。
でも、その計算力を使って『百ます計算 』などを短時間で、時間を計りながら行なうことは、脳が活性し、集中力なども養われていきます。
また『そろばん 』を使った計算や暗算の反復練習も、知能を上げることが分かってきたので、ゆとり教育時代に無くなっていた「そろばん練習」が、公立の小学校でも再開されるようになりました。(※しかし、学校では使い方を覚える程度で、知能が上がるような使い方をしているわけではありません。)
そろばんは、指先を使い、集中力も養われ、暗算やフラッシュ暗算は、右脳を活性させます。
このような脳を刺激し集中力の強化や右脳を活性させるような脳力トレーニングこそが、知能発達につながっていきます。
ただの先行学習は、学校の授業を先取りして覚えただけに過ぎません。
手に入れた道具(ことば・かず)を、どのように使うのかが、重要なポイントとなります。
「知育」とは、『脳力』や『思考力』を鍛える作業でのことであり、
先行学習は、知育のための道具をそろえた程度に過ぎません。。