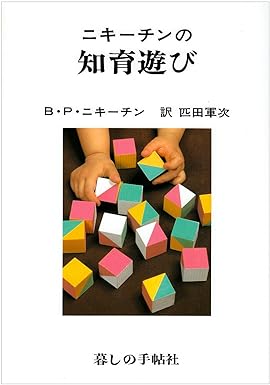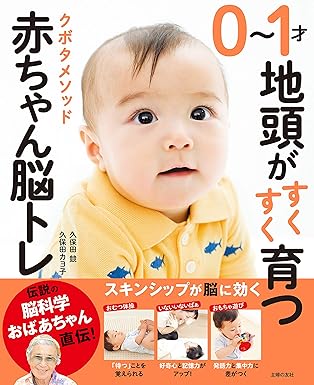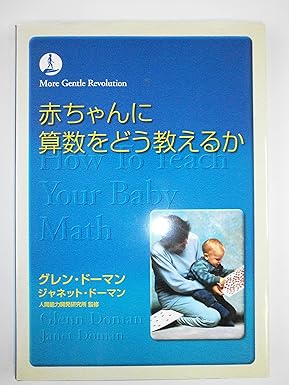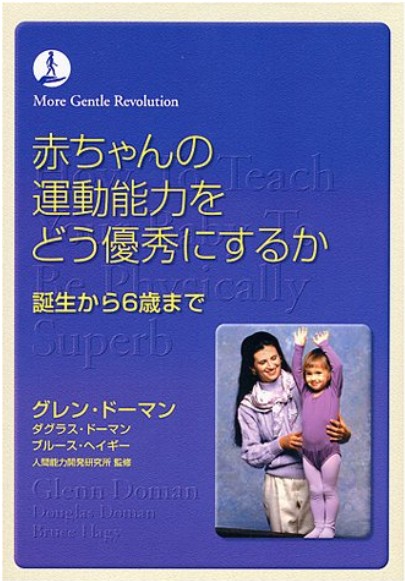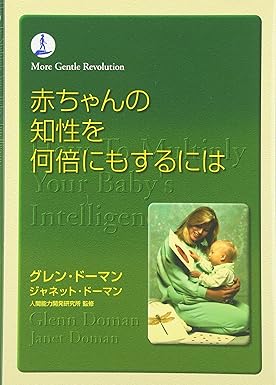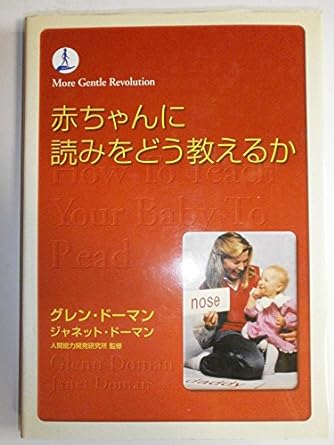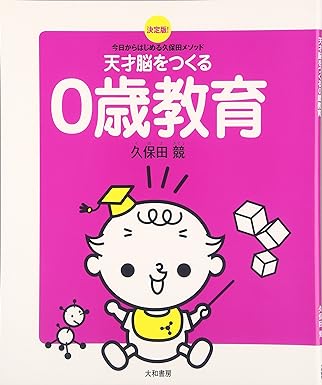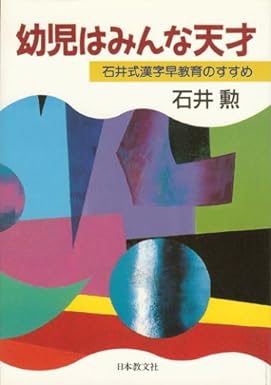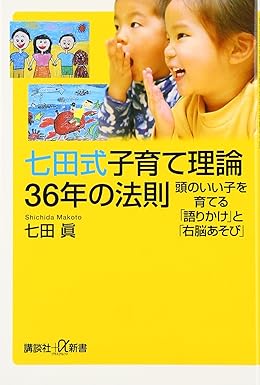-PR-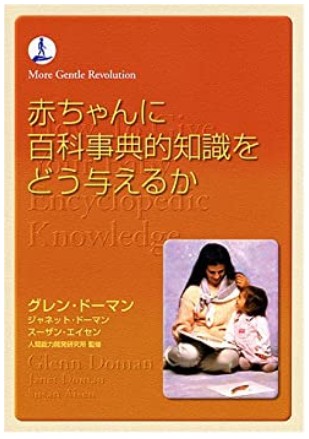
|
| 赤ちゃんに百科事典的知識をどうあたえるか |
赤ちゃんになぜ?言葉の読み・書きを教えるのか。それは、言葉は、コミュニケーションをとったり、知識を刈り取るための道具にもなるからです。
そして、たくさんの本を読むことによって、世の中のことを広く知ることができます。
言葉を覚え始めた幼児期、どの子供も「これは何?」「どうして○○なの?」質問攻めにあうことは、すべてのお母さんが経験されることでしょう。
まさに、それが「赤ちゃんは、学びたがっている!」証拠なのです。
その気持ちを大事にしてあげ、知りたがっていることを何でも教えてあげること!これも、早期教育の1つなのです。
そして、もし、質問されて、自分にも分からないことがあれば、子供と一緒に百科辞典などを使って調べてみましょう。(近い将来、小学校などでの『調べ学習』に繋がっていきます。)
分からないことを放置することなく、一緒に調べて「分かった時の喜びを教えてあげること」です。
そのような繰り返しの中で、いずれは、親の手を借りずとも、自然と自分で調べては知識を増やしていくような習慣が身に付き、自然と知識の豊富な子どもに成長していきます。
また、言葉の意味が分からない赤ちゃん時代や言葉の理解の難しい幼児期、自分の気持ちをうまく表現できないまま小学校に入学した子供たちの様子は、どうでしょう?
自分の気持ちが十分に伝わらず、ダダをこねたり、寝転んで泣きじゃくったり、暴力的になったり‥。
そんな姿に、親も怒鳴ったり、叩いたり‥。子どももストレスがたまる一方になります。親子がそんなコミュニケーションを毎日とっていれば、次第に目の輝きすら失われかねません。(⇒困っときは、オンラインサポートを、ご利用ください。)
乳幼児期に、言語能力や物事への理解力を早く高めて、自分の気持ちを上手に親に伝えることができるようになれば、自分の気持ちを理解してもらえず癇癪をおこす機会も減り、ストレスがたまり難くくなります。それによって、とても気性がよい、明るい子に育っていきます。
言語力を早く身に付けて、コミュニケーション能力を十分育てることは、子育てにおいて、とても有意義なことなのです。